~一歩一歩の「気づき」が未来を変える~
目次
1. 発見:歩行は「ただ歩くこと」ではなかった
脳卒中の後遺症でリハビリをしていると、多くの方が「とにかく歩けるようになりたい」と考えます。
でも実は、歩行はひとつの大きな動作ではなく、小さな動きの積み重ねです。
- 立ち上がる
- 重心を移す
- 足を振り出す
- 片足で支える
- 両足で安定する
こうして分解してみると、「ああ、歩行ってこんなに段階があったんだ!」という発見が得られます。
リハビリは「全体を一気にできるようにする」ことではなく、部分を丁寧に積み上げることだと気づけるのです。
2. 学び:分解トレーニングの具体的方法
では、実際にどのように分けて練習すればいいのでしょうか?
ここでは、自宅で取り組みやすい方法をご紹介します。
(1)立ち上がり練習
- 椅子から立ち上がる動作を繰り返す
- 「お尻を前に」「両足で床を押す」を意識する
→ 下肢の筋力とバランスの土台を養う
(2)重心移動練習
- 手すりにつかまり、左右に体重を移す
- 「麻痺側にもしっかり体重が乗った」と感じられるまで丁寧に
→ 歩行の核心である「片足支持」の準備になる
(3)足の振り出し練習
- 壁や椅子に軽く手を添え、片足をゆっくり前に出す
- つま先が床に引っかからないよう意識する
→ スムーズな一歩のための動作学習
(4)片足立位エクササイズ
- 手すりのそばで麻痺足で立ち、非麻痺足を少し浮かせる
- 「頭と体幹を真っ直ぐに保つ」イメージを忘れずに
→ 歩行の安定性と転倒予防に直結
(5)両足支持での安定練習
- 一歩進んだら、両足でしっかり止まる練習をする
- 「歩く」だけでなく「止まる」も大切
→ 転倒リスクを減らす効果がある
3. 娯楽:ちょっと笑える工夫で続けやすく
リハビリは真剣だからこそ、気持ちが沈みがちになります。
そんなときは「遊び心」を取り入れると続けやすいです。
- 足を振り出すときに「エイッ」と掛け声をつける
- 孫や子どもと一緒に「立ち上がり競争」をしてみる
- バランス練習のときに、鏡に向かって変な顔をしてみる
真剣なリハビリの中に、ちょっとした笑いや癒やしを入れると、毎日の練習が「苦行」ではなく「日課」になっていきます。
4. 感動:できなかった一歩が、家族を笑顔にする
ある患者さんは、脳卒中後に「もう一生、外は歩けない」と思い込んでいました。
でも、「歩行を分解して練習する」ことを始め、少しずつ感覚を取り戻しました。
- まずは椅子から立ち上がれるようになり
- 次に、麻痺足に体重をかけられるようになり
- そして、ついに玄関の外に一歩踏み出したのです。
その瞬間、ご本人も、ご家族も涙ぐんで「できたね!」と喜び合いました。
リハビリの小さな積み重ねは、やがて大きな感動につながります。
5. まとめ:歩行は「部分練習の積み重ね」で変わる
- 歩行は「立つ」「重心移動」「振り出す」「支える」「止まる」の分解動作から成り立つ
- 部分ごとに練習することで、無理なく上達できる
- 娯楽要素を取り入れると、続けるのが楽しくなる
- 小さな一歩の積み重ねが、家族と分かち合える感動を生む
歩行の練習は、ただ歩くことではありません。
「分解して練習すること」こそ、未来を変える一歩なのです。
ゆかわ訪問はりきゅうマッサージ
「退院後のリハビリに不安がある」「歩行をもっと安定させたい」など、どうぞお気軽にご相談ください。
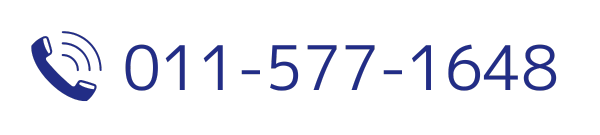

コメント