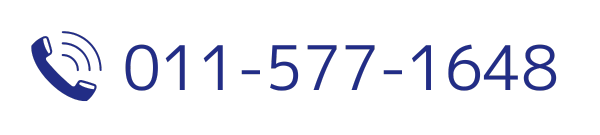

ある日の夕方、
食事の支度中に妻が突然、声を荒らげた。
「なんでそんな言い方するの?!」
「私のことなんて、どうでもいいんでしょ!」
怒鳴ったかと思えば、そのままうずくまって泣き出す。
言い争いをした記憶もないのに、会話が崩れ落ちる。
3ヶ月前に脳出血を発症し、今は自宅療養中の妻。
手足の動きはある程度戻ってきたけれど、心が、別人のように感じる日がある。
これは珍しいことではありません。
脳卒中後に起こる「高次脳機能障害」という、“見えない症状”が関係しているのです。
高次脳機能障害とは、記憶・注意・判断・感情のコントロールなど、
“人らしさ”を司る機能がうまく働かなくなる後遺症です。
外見は元気に見えることも多く、「なぜそんなこと言うの?」「わざとやってるの?」という誤解が起こりやすいのです。
家族としては、
「一体どこまで本人の意思で、どこからが病気の影響なのか」
わからなくなり、心がすり減っていきます。
リハビリ中、あるご家族がこうつぶやきました。
「頑張っているのは分かってる。でも、感情をぶつけられると、正直しんどい。
自分のほうが壊れそうになることがあるんです。」
これは、誰にでも起こりうる“心の限界”です。
こうした思いが重なって、
いつしか「支える」は「背負う」になり、自分を見失っていきます。
ここで必要なのが、「メタ認知」の視点です。
それは、
自分自身の思考・感情・判断を、“一歩上の視点”から眺め直すこと。
たとえば、こう問いかけてみてください。
このように“心の内側の声”を言葉にする習慣がついてくると、
目の前の感情の爆発を、“攻撃”ではなく“表現”として受け取れるようになっていきます。
感情を抑えられない人に、
「落ち着いて」と言っても逆効果になることが多いのはご存じでしょうか?
むしろ、「何も言わずに、そっと隣に座る」
「深呼吸する音をわざと聞かせる」
「お茶を淹れて渡す」
といった“言葉のいらない共鳴”のほうが、効果的なときがあります。
なぜなら、感情は“理屈”ではなく“身体”の反応だから。
そこで有効なのが、鍼灸などの身体からの介入です。
当院では、感情不安定をともなう高次脳機能障害の方に対して、次のような施術を行っています。
| アプローチ | 目的 | 効果の実例 |
|---|---|---|
| YNSA(頭鍼) | 脳の代償領域を刺激し、感情抑制や集中力を整える | 「急な怒り」が減った、「思考がクリアになった」と報告多数 |
| 自律神経調整(腹部・背部) | 副交感神経を高め、情緒の安定を促す | 睡眠改善、不安軽減、感情の波が緩やかに |
| 経絡調整+手足末端刺激 | 脳幹と末梢神経をつなぎ直す | 手足の違和感・しびれ・苛立ちが軽減 |
ここであらためて考えてみたいのは、
「寄り添う」とは何か?という問いです。
「相手の状態に合わせて、自分を犠牲にすること」ではありません。
「正しさを教えること」でもありません。
寄り添うとは──
“共に揺れながらも、壊れずにそばにいる力”を、
少しずつ育てること。
そしてそれは、自分自身の感情にも、優しくなることから始まります。
そして、“体から変えていく回復”も、確かに存在する。
私たちは、その静かな道を一緒に歩く鍼灸院でありたいと願っています。
ゆかわ訪問はりきゅうマッサージ
「退院後のリハビリに不安がある」「歩行をもっと安定させたい」など、どうぞお気軽にご相談ください。
コメント